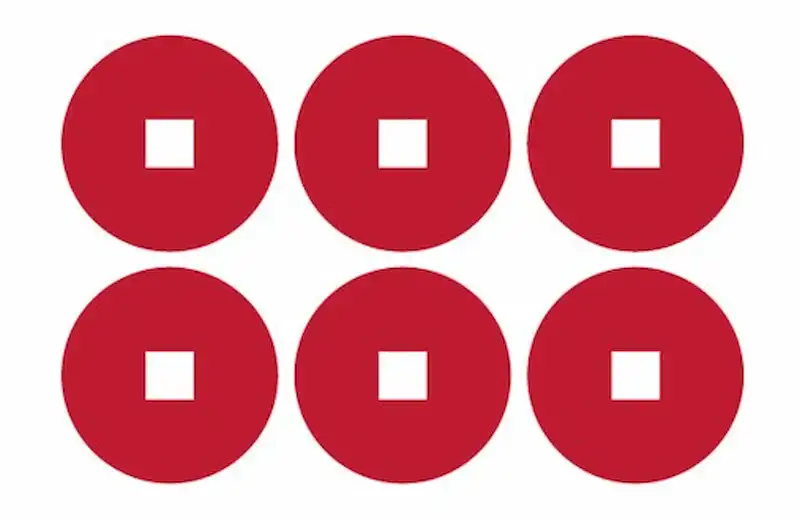
真田信繁の生涯は、戦国時代末期の激動そのものです。大河ドラマ:真田丸を観て真田信繁の物語を辿り、その史実と、物語の魅力を高めた演出部分を整理します。
1. 武田家滅亡と外交による家名存続

武田勝頼と織田信長をめぐる戦いの詳細を知る中で、物語は幕を開けます。武田家は、家臣の裏切りによって勝頼が討たれ滅亡しました。この混乱を経て、真田家は存続のために上杉氏につくか、織田氏につくかという至難の選択を迫られます。
織田家に仕えた真田家は、信濃を任された滝川一益の指揮下でやり取りを行います。一益はドラマなどではあまり取り上げられない人物ですが、真田家との駆け引きは重要な場面でした。
これまでの大河ドラマでは、信長、秀吉、家康など関西(畿内)をメインとしたストーリーが多く描かれてきましたが、この作品では関東や甲信越といった地域の情勢が詳細に描かれており、その背景を知ることができたのも大きな魅力でした。
2. 人質外交と真田家の孤立無援

その後、信繁は上杉家に人質となり、上杉景勝との間で親交を深めていきます。
しかし、徳川軍が大軍で真田家を攻めた際(第一次上田合戦)、上杉領にいる信繁が一時的に戻り応戦して徳川軍を追い返した、という描写があります。(※これはドラマの演出であり、一般的な史実では、信繁はこの戦いに参戦していません。撃退したのは父・昌幸が中心です。)
信繁はさらに豊臣秀吉の元へ移り、近習(馬廻衆)として仕えます。秀吉のそばで、石田三成や義父となる大谷吉継といった重臣たちと出会い、様々な出来事に対峙していくことになります。
この物語では、真田幸村(信繁)が主役ではありますが、その父である真田昌幸が稀代の策士として非常に魅力的に描かれており、ドラマの主要な人物として光を放っていました。また、真面目で真っ直ぐな性格として描かれた兄の真田信幸も加わり、真田家の物語としての面白さを深めています。
3. 沼田裁定から関ヶ原の岐路

沼田領の帰属をめぐっては、北条、真田、徳川の間で話し合いが行われました。(※話し合いの場所や参加者はドラマの演出による可能性があります。)北条氏がこの裁定を覆し、名胡桃城を攻めたことが、秀吉が天下人として介入する小田原征伐のきっかけとなります。
信繁は、大谷吉継の娘である春(竹林院)を正室に迎えます。
その後、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発。真田昌幸は、この戦いが長引くことを予測し、第二次上田合戦を起こします。この戦いで昌幸が天下取りを狙ったとされる描写もありましたが、(※これはドラマの解釈です。通説では西軍勝利による豊臣家存続を目指したとされます。)しかし、関ヶ原はあっけなく短期で決着してしまいました。
4. 九度山での雌伏と大坂の陣での最期

関ヶ原の結果、罪人となった信繁と昌幸は、高野山のふもとの九度山に幽閉されます。また、九度山での生活費を賄うため、信繁が真田紐を発明し売ったという逸話も残されています。(※これは有名な創作・逸話であり、史料で確認できる事実ではありません。)
大坂の陣が始まる頃、豊臣方からの誘いを受けた信繁は九度山を脱出し、大坂城へ入ります。ここで信繁は、父の名から一字を取り幸村と名前を改めたとされます。(※「幸村」という名は信繁の生存中に確認できる史料には登場しない創作名・通称です。)
大阪城では、後藤又兵衛、毛利勝永、長曾我部盛親ら名だたる浪人衆と出会い、大阪軍の主戦力として戦います。特筆すべきは、冬の陣、夏の陣の戦いが10話近くの尺を使って丁寧に描かれた点です。冬の陣では、築城した真田丸で徳川軍を撃退し、名を轟かせました。
夏の陣では、徳川家康の本陣直前まで迫る猛攻を見せますが、旗印を城に戻したことなどが原因で兵士の士気が下がり負けたとされます。(※旗印に関する記述はドラマの演出です。敗因は兵力差や味方の総崩れが主因とされます。)
この真田信繁の物語は、史実に基づく豪胆な活躍だけでなく、魅力的な家族の描写や、物語として加えられた演出・逸話によって、今なお人々の心を捉え続けています。
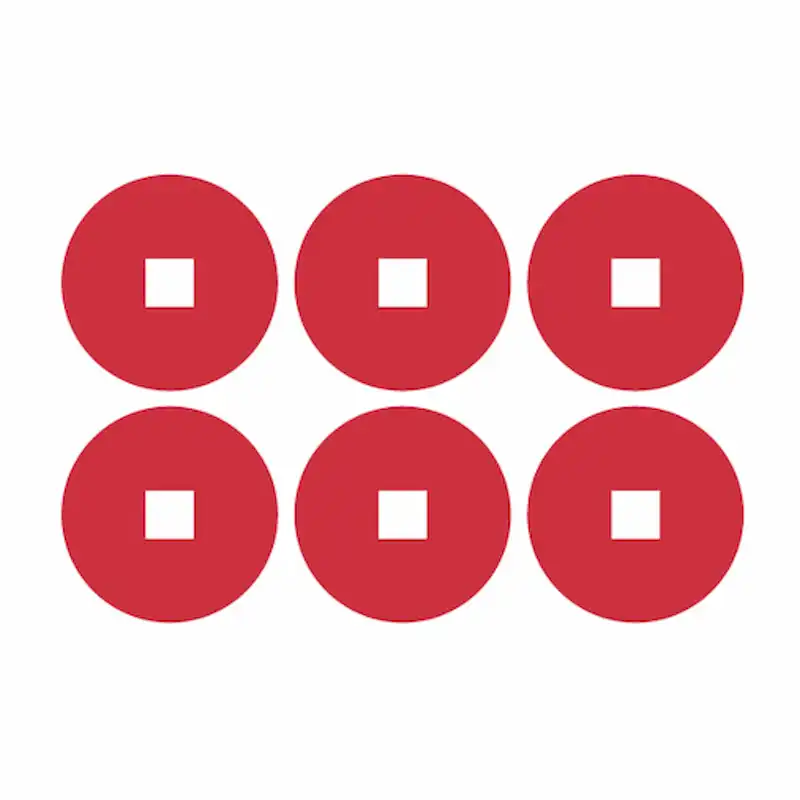

comment