🌸「冷酷な信長」ではなかった?——代々木で感じた“天下人”の素顔

歴史好きの私にとって、“織田信長”という人物は、何度も何度も振り返りたくなる存在です。
そんな信長の新たな一面を知ることができるかもしれないと思い、25年11月15日、代々木 国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された講演会「戦国近江へのいざない 元亀争乱と天下人織田信長の誕生」に参加してきました。
この講演に足を運んだのは、ただの知的好奇心からだけではありません。私は「Following The Shogun」というプロジェクトを通して、歴史を多角的に捉える視点を発信しています。今回の講演も、そんなテーマにぴったりだったのです。
🧭 元亀争乱——信長にとっての“転機”ではなく“通過点”
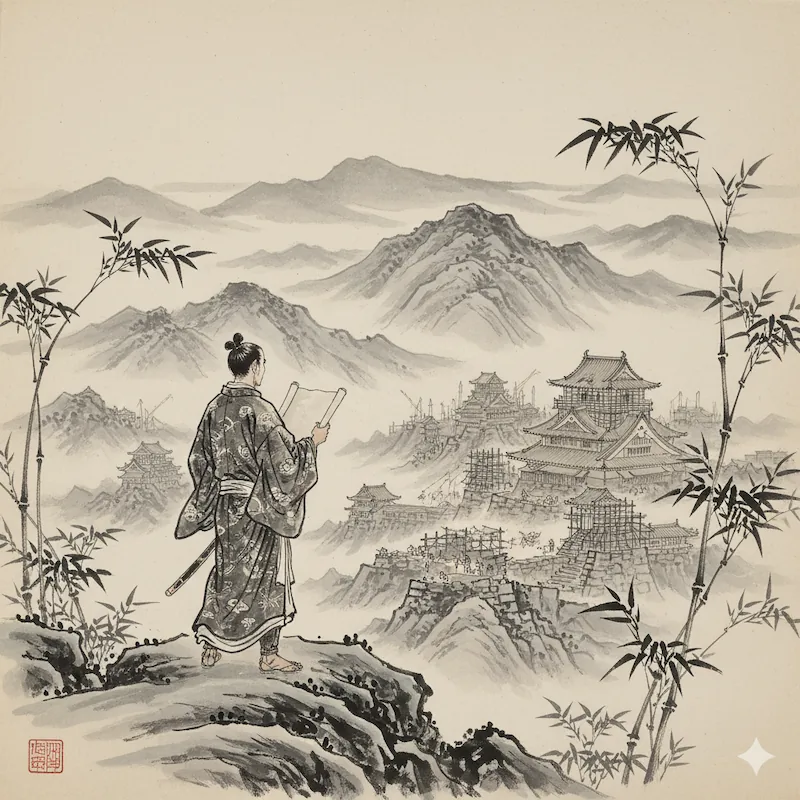
講演では、信長が戦国大名から天下人へと変わる過程としての「元亀争乱」が、ただの地方戦ではなく、信長自身の転機とも言える大きな流れの一部として描かれていました。
この争いを経て、信長は安土城の築城へと進み、室町幕府の再建、そして自らの立場の確立に向かっていきます。
従来の「信長=革新者で、力で突き進む人物」といった印象に対し、ここでは「調和を求め、秩序を模索する思慮深きリーダー」という新しい信長像が語られていたのが印象的でした。
🤝 信長と義昭——友情とすれ違い、そして“本気”の復興願望
中でも私が「へえ!」と思わず声をもらしたのが、足利義昭との関係性に関する部分です。
これまで私が目にしてきた資料やドラマでは、信長は義昭の権威を利用して自らの立場を強め、「おいしいところだけ取っていた」という印象が強く描かれていました。
しかし今回の講演で、信長が義昭を丁寧に扱い、彼の将軍としての立場を尊重しようとしていたという話を聞き、「そうではなかったのかもしれない」と思い始めたのです。
秩序を守るため、時には義昭に厳しい態度を取ることもあった——それが義昭からすると“気に食わない”と映った可能性もありますが、それでも信長は義昭を決して見捨てず、最後まで関係修復を望んでいたという点に、私は深い人間味を感じました。

この講演を聞きながら、私は次第に、信長は本気で室町幕府を再建したかったのではないか、と感じるようになりました。義昭を追放したあとも命までは取らず、むしろ共にやっていく道を探していた——その姿勢こそが、信長がただの覇者ではなかった証拠だと思えるのです。
🏯 浅井長政の“裏切り”——誇りと折り合いの葛藤
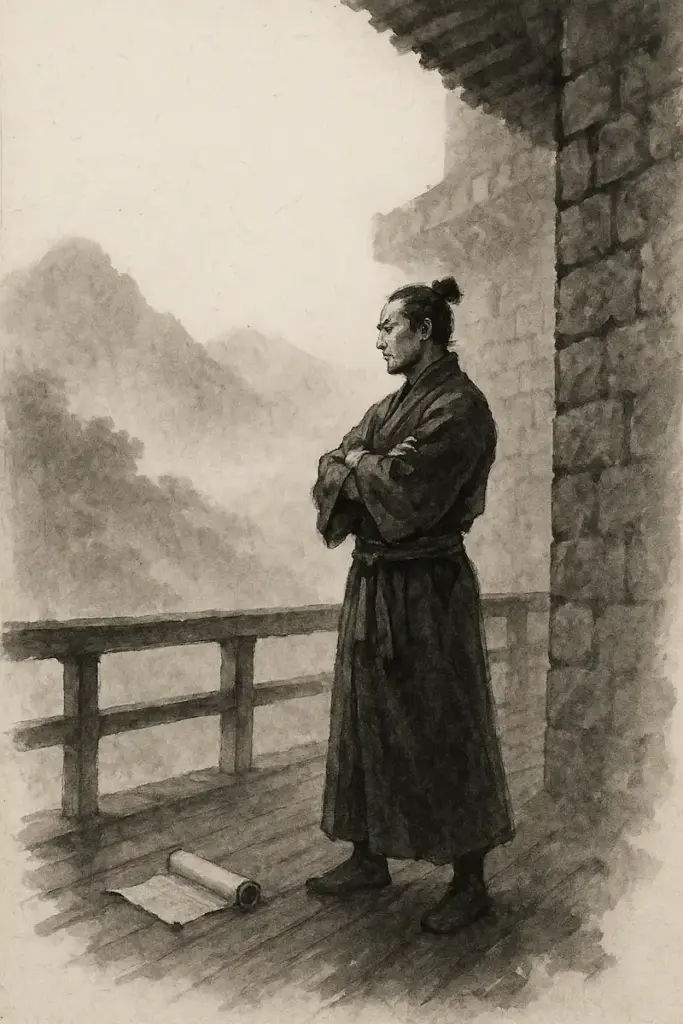
また興味深かったのは、浅井長政が信長に背いた理由についての新しい解釈です。
これまで私は、浅井が朝倉氏との軍事同盟を優先した結果、信長を裏切ったのだと理解していました。けれど、近年の研究ではそれだけでは説明できないという見方があるそうです。
それは、浅井家が「織田の家臣になること」を強く拒んだという視点。
つまり、独立した戦国大名としての誇りを守るため、信長の秩序に組み込まれることを良しとしなかった——その結果が裏切りという形になったというのです。
信長は天下統一への道を歩む中で、ただ力で従わせるのではなく、相手の立場や誇りとどう折り合いをつけるかに悩んでいたのではないか。浅井家とのすれ違いにも、そうした“葛藤”があったのだと考えると、歴史の奥行きがぐっと広がります。
👥 会場の空気と“集中力”
講演では広く知られている話題も多く扱われましたが、そうした部分では会場の集中力が一時的にゆるむような空気も。
おそらく、私を含め多くの参加者が歴史に詳しく、既知の話よりも“新たな視点”を求めて来場していたからでしょう。
その中で、義昭との関係や浅井長政の動機といった、深掘りされたテーマには皆が前のめりになって耳を傾けていた印象です。
🔭 “正しさ”より“多様さ”を楽しむ歴史へ
今回の講演は、単に「信長はこうだった」と断定するものではなく、「こういう見方もできるのではないか?」という問いかけの連続でした。
その中で私は、自分の中にあった信長像が少しずつ変わっていくのを感じました。
これからも私は、歴史を一つの視点だけで捉えるのではなく、時代背景や人物の心情にまで思いを巡らせながら、多角的に読み解いていきたいと思います。
信長という存在を通して、歴史の奥にある“人間らしさ”に触れられた、そんな一日でした。

comment